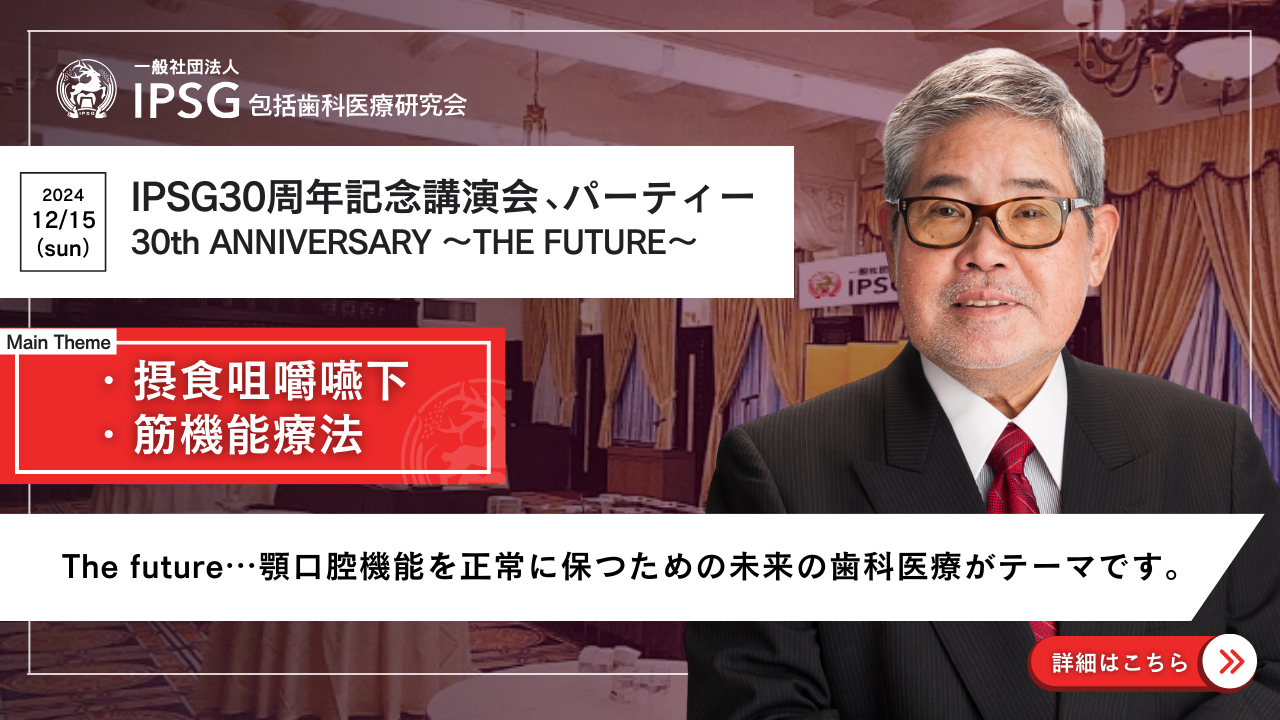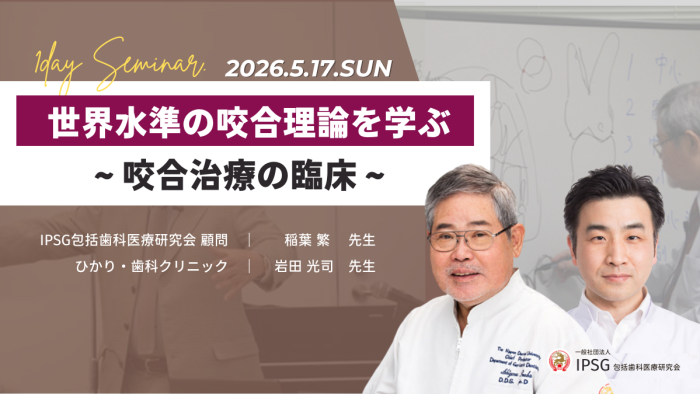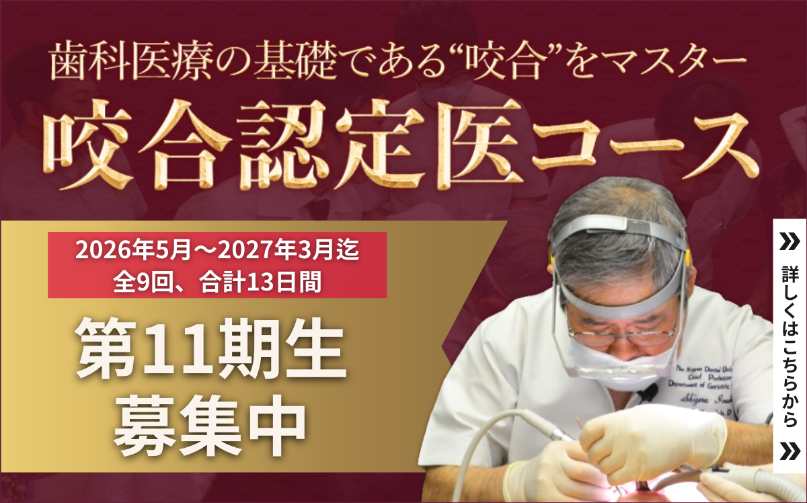Questions歯科治療に関するQ&A
Q:稲葉先生の講義に出てくる、顎運動の『将棋の駒理論』について教えてください
また、当時海外からの咬合理論が大半を占めていたので、日本的な将棋の駒で世界に伝えたかったということがあります。
『将棋の駒理論』は私が作った顎運動の理想的な形態を表すものです。
顎の運動は回転Rotationと滑走Translationに分かれており、中心位で開口した時は関節内で下顎は回転します。
さらに開口して行くと下顎は滑走を始め関節内の上壁に沿って前方に滑走し、さらに大きく開口して最大開口します。
前方運動でも同様に、中心咬合位で最大面積で接触していた歯は前方運動すると関節部では上壁に沿って前方へ滑走していきます。
その時前方の歯列では前歯が誘導して臼歯は離開し、臼歯の側方力を防止します。
側方運動では片側の下顎頭は回転し、その反対側は滑走します。
回転側(作業側)では犬歯が誘導し、その他の歯は離開します。
これを『犬歯誘導』といいます。
この時下顎骨を上方より投影して見ますと、後方は両側の関節と両側犬歯と前歯の形態で成す外形は五角形をつくります。
これはあたかも『将棋の駒』に良く似ている五角形です。
五角形を分解してみると両側の関節を底辺として三角が三つに分解することができます。
下顎運動はこの三角の合成で行なわれており、下顎頭を底辺として三角形の移動でスムーズに行なわれるのが理想的な形態となります。
この三角は面積が大きければ大きい程安定しており、下顎運動をスムーズに行なわれることになります。
もしこの時、下顎の運動中に臼歯が接触すると、三角は面積を縮小し、梃子現象が誘導されます。
下顎頭は不安定となり、顎関節もそれに伴い不安定となり、時として関節円板の偏位を招くことがあります。
これを防止するための理論として「五角形の理論」いわゆる『将棋の駒理論』と名付けました。
*:..。o○☆゜・:,。*:..。o○☆*:゜・:,。*:.。o○☆゜・:,。
先生方が診療する時に座っているチェアーも5つ脚があるかと思います。
両側顎関節と両側犬歯、そして切歯の五角形。
五角形が一番安定するのですね!
IPSGとは
IPSG包括歯科医療研究会は、「医療には最善の方法が実行されるべきである」という稲葉繁先生の信念のもと、海外で学んだ確かな技術を日本の歯科医師に広めることを目的とした研究会です。
「顎関節症」「テレスコープシステム」「総義歯」「摂食嚥下」の4本の柱を軸に、診療姿勢から全顎治療までを基礎から応用まで学べるプログラムを提供しています。専用のセミナールームには最新の設備を完備し、実践的な研修が可能です。
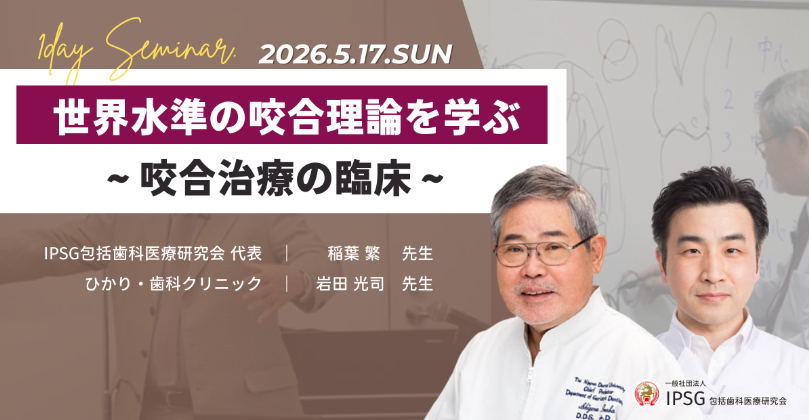
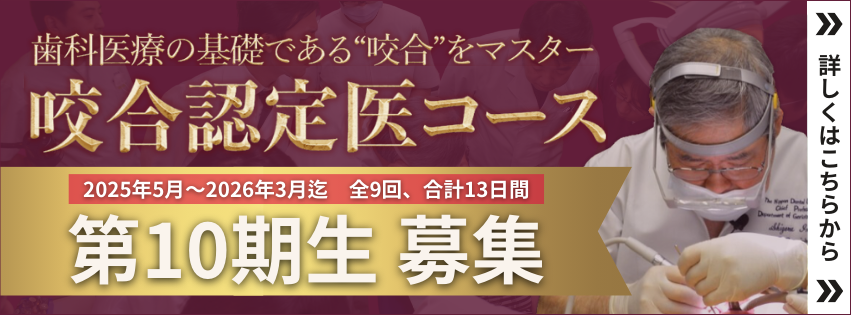
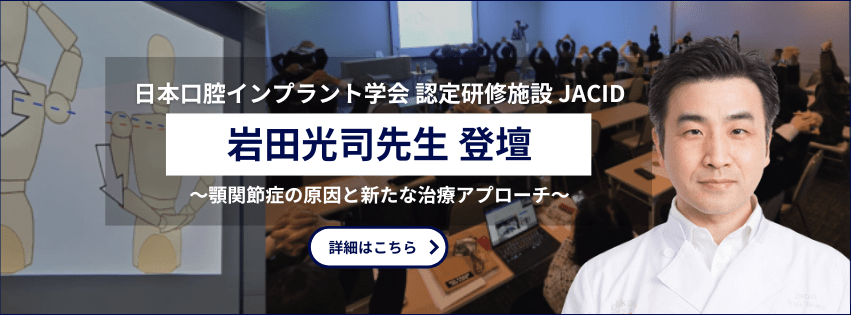
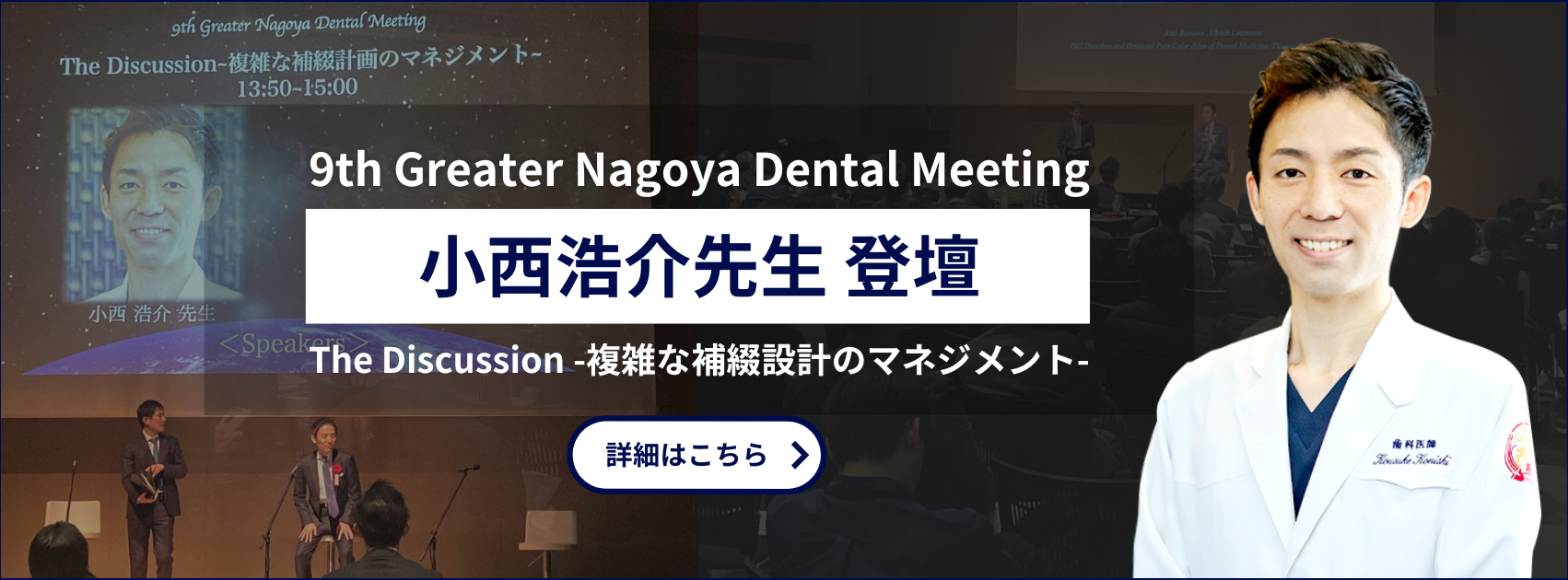

開催予定のセミナー
| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |
|---|---|---|
| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |
Mail magazineIPSGの無料メールマガジン
歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。
IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。
咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。