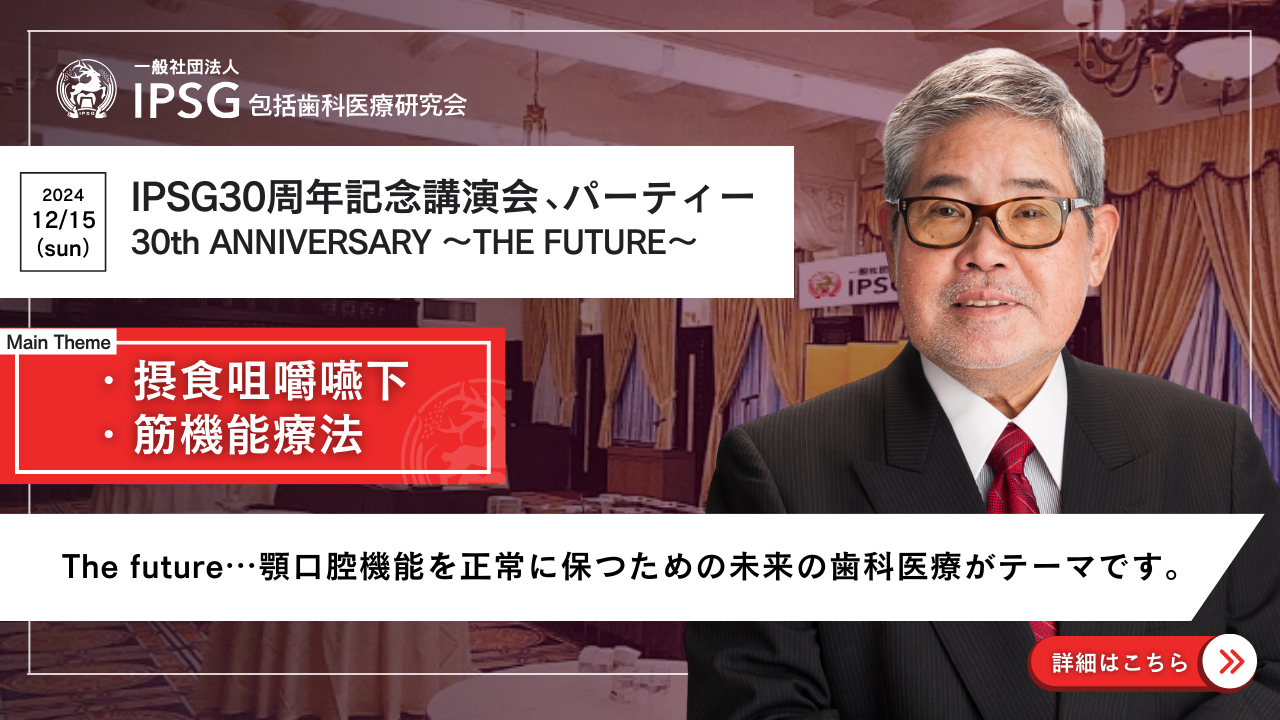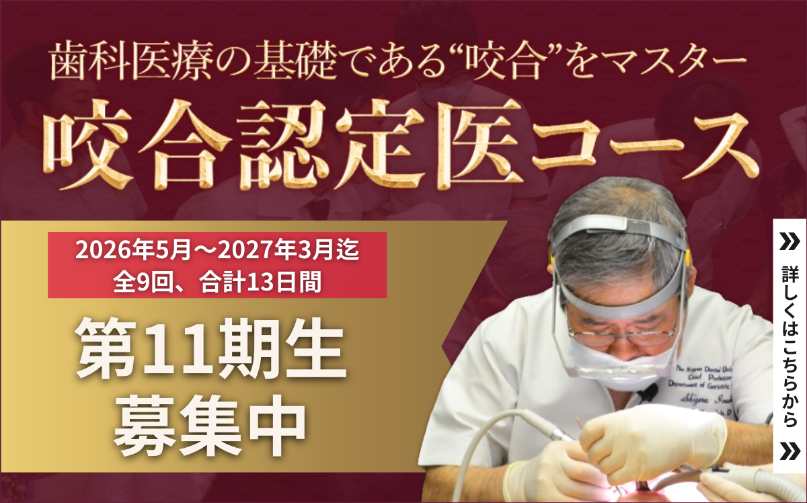Questions歯科治療に関するQ&A
Q:咬合調整について、側方運動をした際に印記されたところの干渉を削るときに、咬頭を削るか、溝を作るかの判断をどのようにしたらよいでしょうか?
咬合調整には、ギシェー法、スチュワート法、ラウリッツェン法、ジャンケルソン法などがありますが、ギシェー法は一番臨床に取り入れやすいと思います。
それは最初に中心位の確立を行って、続いて偏心位、特に前方位では前歯のみが誘導して臼歯を離解させます。次に、側方位では作業側の犬歯が誘導し、平衡側を離解させます。
作業側の臼歯では下顎の頬側斜面の接触を除去します。上顎では頬側の内斜面を除去します。
最後に中心位から動き始めのニアセントリックの調整、干渉をとります。
今回のご質問、側方運動の時の作業側は歯列の咬合平面をみだしているときは咬頭であっても削っていいと思います。
特に上顎の頬側咬頭、下顎の舌側咬頭を削ることはあります。平行側の場合は、咬頭頂は、通りやすいように溝をつけ、干渉をのぞきます。
*:..。o○☆゜・:,。*:..。o○☆*:゜・:,。*:.。o○☆゜・:,。
IPSG YouTube チャンネルにて「咬合面の8要素」〜ABCコンタクト、斜走隆線〜について動画で詳しくお伝えしております。
歯科医師、歯科技工士人生が、たったの10分で変わってしまうような動画ですので、ぜひご覧いただけると嬉しく思います。
先生方の臨床のお役に立つことができればと思うので、ぜひご活用ください。
IPSGとは
IPSG包括歯科医療研究会は、「医療には最善の方法が実行されるべきである」という稲葉繁先生の信念のもと、海外で学んだ確かな技術を日本の歯科医師に広めることを目的とした研究会です。
「顎関節症」「テレスコープシステム」「総義歯」「摂食嚥下」の4本の柱を軸に、診療姿勢から全顎治療までを基礎から応用まで学べるプログラムを提供しています。専用のセミナールームには最新の設備を完備し、実践的な研修が可能です。
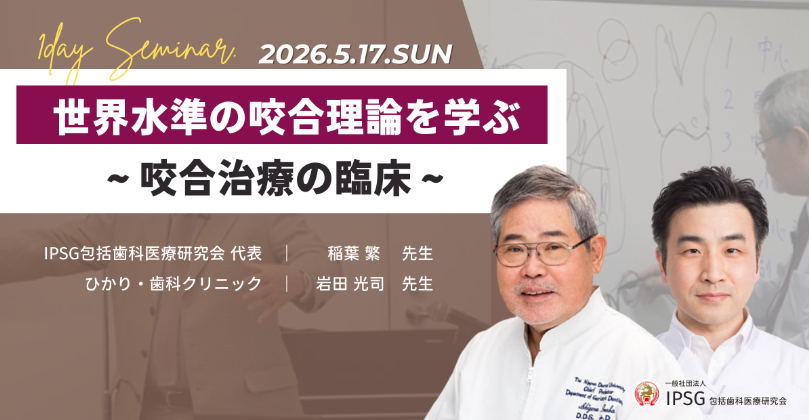
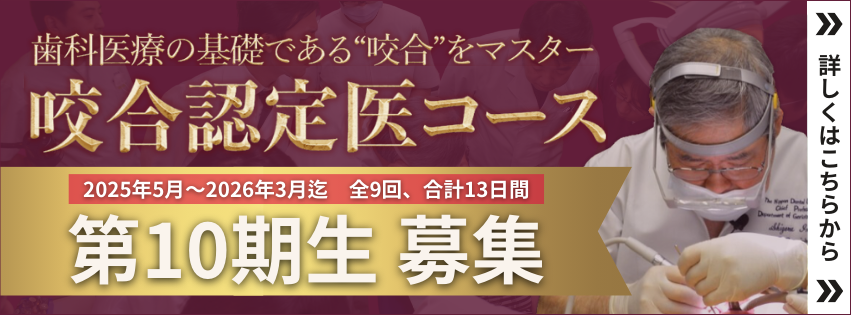
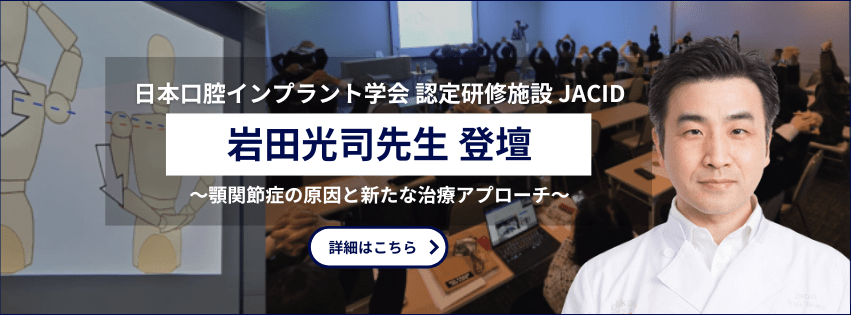
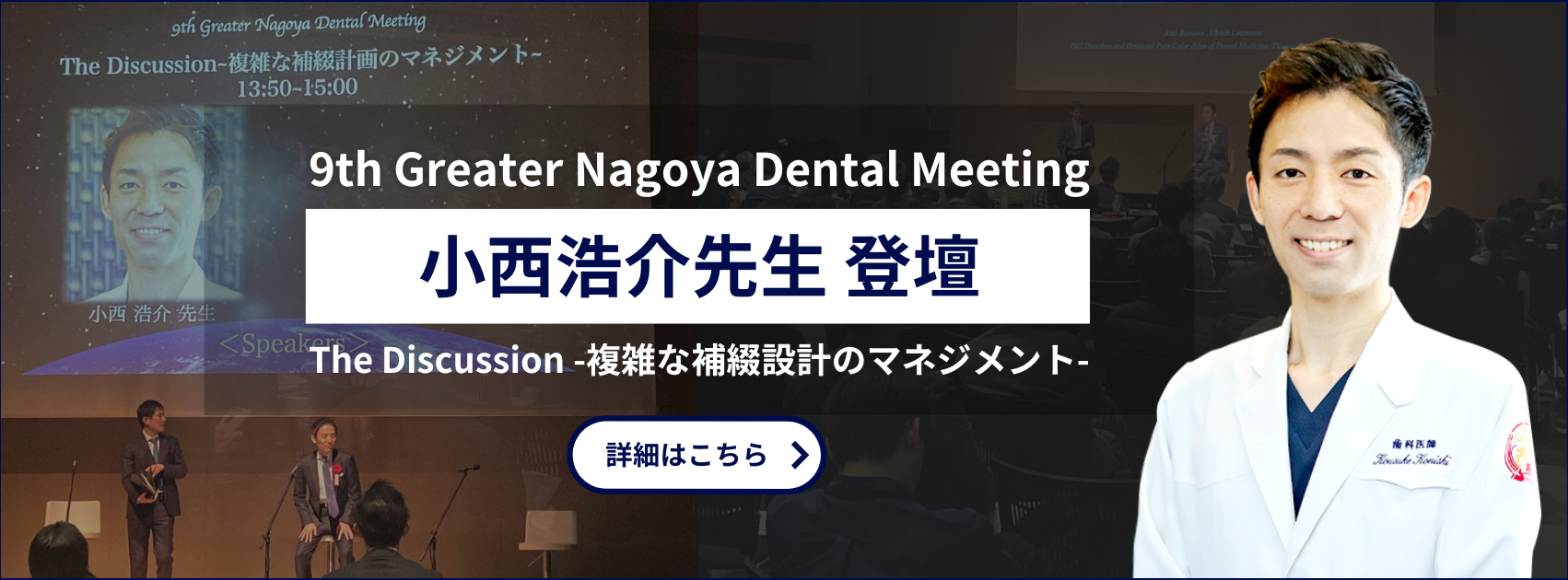

開催予定のセミナー
| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |
|---|---|---|
| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |
Mail magazineIPSGの無料メールマガジン
歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。
IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。
咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。