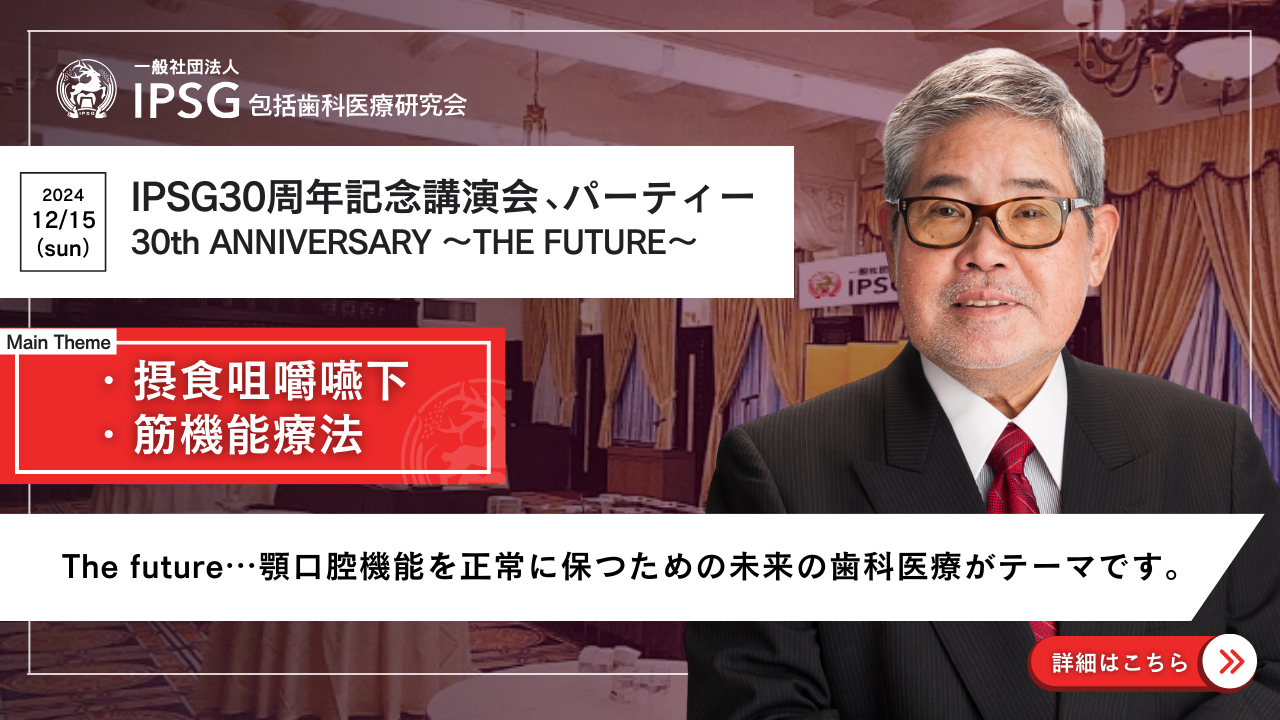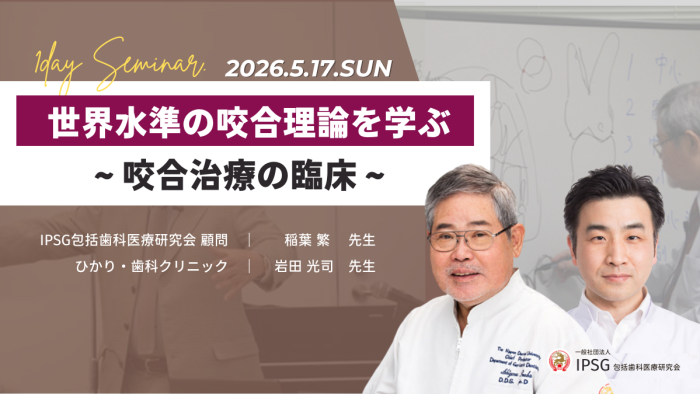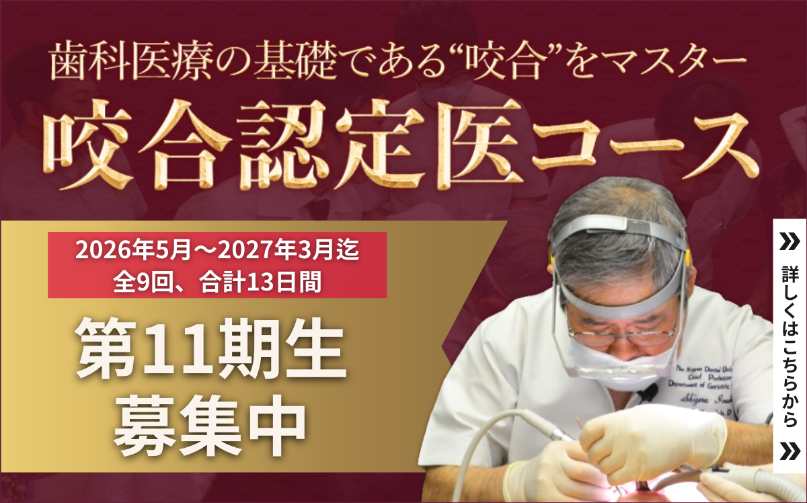Questions歯科治療に関するQ&A
Q:耳珠前縁から12mm前でそこから5mm下がったところが顆頭点(ヒンジポイント)であるとありましたが、どの方向に向かって12mmでしょうか。
耳珠前縁から12mm前でそこから5mm下がったところが顆頭点(ヒンジポイント)であるとありましたが、どの方向に向かって12mmでしょうか。
また、咬合学辞典によるとP398,399にSolnit(1988)はターミナル・ヒンジアキシスの代わりに平均値法で後方基準点として、耳珠上縁と外眼角を結ぶ線に沿って耳珠上縁から11mm前方で5mm下方の点を取れば、80~90%の症例で満足すべき結果が得られると書いてありますが、どちらを使ったら良いでしょうか。
平均的顆頭点についてはGysi以来多くの研究があり未だに決定的な値は決まっていないのが実情です。
確かにSolnit の11mmも一つの研究として良いと思いますが、他の研究結果としては平均的顆頭点としてGysiは外耳上縁と外眼角を結ぶ線上で外眼角の前方13mmの点、Hanauはフランクフルト面上で外耳道前方12mmの点、LundeenはGysiの示した顆頭点の下方3mmを示している。
保母は平均的顆頭点として外耳道上縁から外眼角に向って13mm前で5mm下がったところを推奨しています。いずれにしても平均的顆頭点にはこれだという不文律はありません。
私は日常臨床では外眼角に向かって耳珠上縁より12mm前方で5mm下方の位置を使っていますが、それはGuichetの考えによるDenar社のルーラーでは12mm前で5mm下方に穴が開いており平均的顆頭点としていることを根拠にしています。
実際このデータを応用しようとしても計測の仕方や人間の耳珠の形などで1mmや2mmは誤差として考えても良いと思います。
IPSGとは
IPSG包括歯科医療研究会は、「医療には最善の方法が実行されるべきである」という稲葉繁先生の信念のもと、海外で学んだ確かな技術を日本の歯科医師に広めることを目的とした研究会です。
「顎関節症」「テレスコープシステム」「総義歯」「摂食嚥下」の4本の柱を軸に、診療姿勢から全顎治療までを基礎から応用まで学べるプログラムを提供しています。専用のセミナールームには最新の設備を完備し、実践的な研修が可能です。
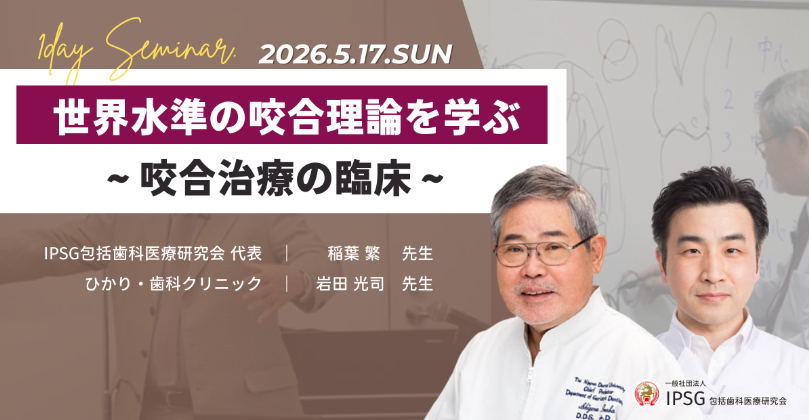
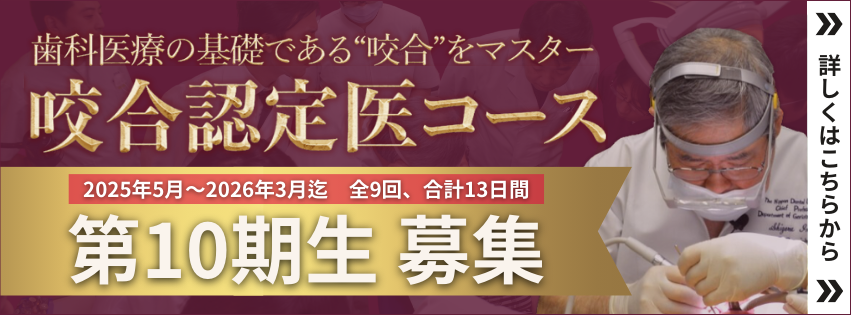
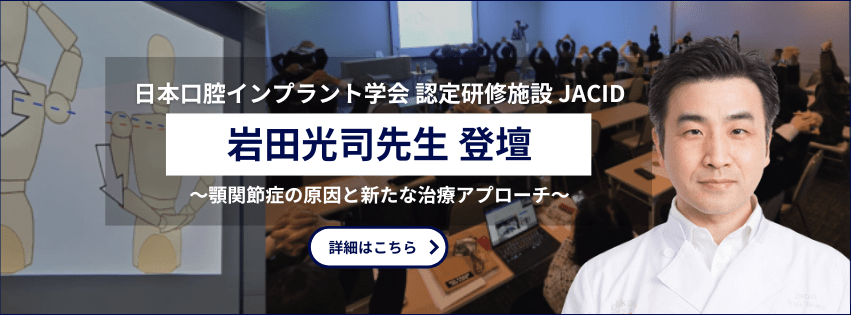
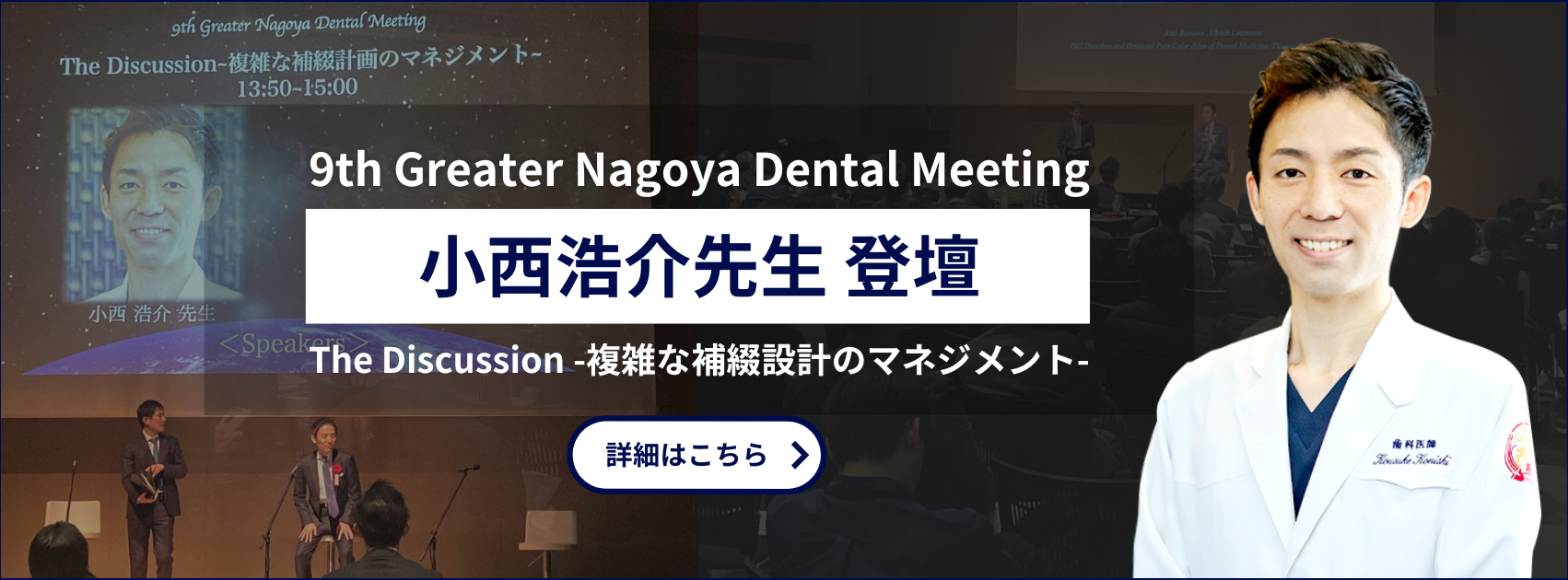

開催予定のセミナー
| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |
|---|---|---|
| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |
Mail magazineIPSGの無料メールマガジン
歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。
IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。
咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。